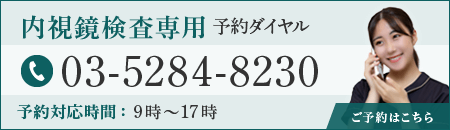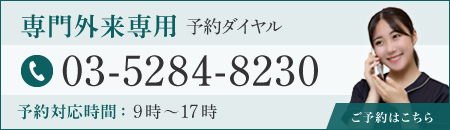「胃がパンパンに張って苦しい」
「お腹が空いていても胃が張る」
腹部膨満感は、胃腸が膨らみ、お腹が張ったり重苦しく感じたりする症状です。腹部の張りや重苦しさ、圧迫感だけでなく、吐き気や便秘を伴う場合もあります。また、症状の発生パターンも個人差があり、常に感じる人もいれば、朝だけ、あるいは緊張したときにのみ感じる人もいます。
腹部膨満感の原因は胃に限らず、腸にも関係している可能性が高いです。消化器系の機能障害、炎症性腸疾患、腸閉塞、消化器系の腫瘍などが考えられます。これらの可能性を適切に診断するためには、内視鏡を得意とする医療機関で検査を受けるといいでしょう。
胃カメラや大腸カメラを希望する際には、東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックにご相談ください。
当プラザには経験豊富な内視鏡専門医が在籍し、高性能な胃カメラ・大腸カメラも完備しています。これにより、症状の原因を迅速かつ正確に特定することが可能です。
また、当プラザは北千住駅から徒歩約2分という好立地にあり、土日も検査を実施しているため、仕事帰りや週末の受診が可能です。さらに、女性に配慮した女性専用の検査室や女性医師による診察も行っています。専門的な知識と最新の技術を駆使して、患者さん一人ひとりの健康をサポートいたします。症状が気になる方は、お早めにご連絡ください。
目次
胃がパンパンに張って苦しい原因
胃が張って苦しい原因には、疾患の他に生活習慣も関係しています。食生活が乱れていると、胃粘膜があれてしまい正常な機能が難しくなるためです。
生活習慣が乱れている
お腹の張りの主な原因は腸内に溜まるガスであり、これは生活習慣の乱れと深く関連しています。早食いや、よく噛まずに食べる習慣があると、空気も一緒に飲み込むことにつながりますし、暴飲暴食や刺激物の過剰摂取は腸内環境を乱すと考えられています。さらに、ストレスや睡眠不足も消化器系の機能に悪影響を及ぼし、ガスの蓄積を促します。
これらの問題を改善するには、ゆっくりとよく噛んで食事をし、消化の良い食品を選び、規則正しい食生活を心がけることが重要です。
また、ストレス管理と十分な睡眠の確保も効果的です。
これらの対策を日常生活に取り入れることで、お腹の張りを軽減できる可能性があります。ただし、症状が持続する場合は、専門医への相談をおすすめします。
胃粘膜が荒れている
胃の内側を覆う粘膜が荒れると、胃酸と粘液のバランスが崩れ、お腹の張りを感じやすくなります。この状態が進むと胃潰瘍になり、胃の壁が傷つき、重症化すると穴が開く危険性があります。
空腹時の胃の張りや粘膜の荒れは、主に胃酸の出しすぎや自律神経の乱れが原因です。通常、胃酸は食事時に出ますが、空腹時に多く出ると粘膜が刺激され、痛みや炎症を引き起こします。
また、自律神経の乱れも胃酸の過剰分泌につながります。これらの問題を防ぐには、規則正しい食生活とストレス対策が大切です。症状が続く場合は、専門医に相談することをおすすめします。
何らかの病気が影響している
上記に思い当たることがない場合は、何らかの疾患を原因にお腹が張っている可能性が高いです。
胃がパンパンに張る原因として考えられる病気には、下記のようなものがあります。
- 慢性胃炎
- 胃拡張
- 胃下垂・胃腸虚弱(機能性胃腸症)
- 過敏性腸症候群
- 腸閉塞(イレウス)
- 巨大結腸症
- 大腸がん
胃拡張とは、 胃潰瘍や胃がんの影響で、胃の内容物が十二指腸に押し出されなくなり、胃が異常に大きくなってしまう状態のことです。ストレスや生活習慣の乱れを原因とし、腹部膨満感や便秘、吐き気といった症状が現れます。
そのほかに、お腹が張る原因には、暴飲暴食や消化の悪いものの食べ過ぎ、自律神経の乱れなどが考えられます。
思い当たることがなく胃が張った状態が続く際には、早めに消化器内科を受診しましょう。
胃が張って苦しい時に想定される隠れた疾患
胃が張って苦しい状態が長く続く際には、病気が隠れてることがあります。
便秘や過敏性腸症候群を放置し続けると、症状が悪化してしまい治療が長期化する恐れが出てきてしまいます。
便秘
便秘は、胃が張る原因として頻繁に見られる症状の一つです。便秘になると、腸の動きが鈍くなり、便やガスが体外に排出されにくくなります。その結果、腸内に大量の便やガスが蓄積され、腸管内の圧力が上昇し、胃が張る状態を引き起こします。
便秘の主な原因としては、腸内細菌のバランスの乱れが挙げられますが、運動不足や水分摂取不足なども要因となり得ます。また、胃下垂の方は消化不良になりやすく、胃が腸を圧迫することで便秘を引き起こしやすい傾向があると言われています。
便秘の予防には、食物繊維を積極的に摂取することが効果的です。食物繊維には、腸の動きを促進する不溶性食物繊維と、便を軟化させる水溶性食物繊維があります。日々の食事では、栄養バランスに加えて食物繊維の摂取量にも注意を払うようにしましょう。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(IBS)は、消化器に器質的な異常が見られないにもかかわらず、腹痛や便秘、下痢といった便通異常を慢性的に繰り返す疾患です。この症状には、しばしば腹部膨満感が伴います。
その結果、お腹の鳴る音が増えたり、おならの回数が多くなったりすることがあります。また、緊張やストレスにより胃痛が生じ、便通異常を引き起こす可能性が高まることも特徴的です。
過敏性腸症候群の症状は、適切な食生活の見直しによって緩和できることが多いです。たとえば、刺激物を控えたり、規則正しい食事時間を守ったりすることで、症状の改善が期待できます。また、ストレス管理や十分な睡眠も重要な要素となります。
しかし、これらの症状を放置し続けると、より深刻な合併症を引き起こす可能性があります。そのため、持続的な腹部不快感や便通異常が気になる場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
呑気症
呑気症は、無意識のうちに過剰な空気を飲み込むことで、食道や胃、腸に空気が溜まる状態を指します。医学的には「空気嚥下症」とも呼ばれ、胃が張る原因の一つとして知られています。この症状は、早食いや炭酸飲料の過剰摂取、また日常的なストレスなどが要因となることが多いです。
呑気症の治療においては、まず食生活や生活習慣の見直しが効果的とされています。たとえば、ゆっくり食事をする、炭酸飲料を控える、ストレス解消法を見つけるなどの工夫が挙げられます。しかし、症状が改善しない場合は、医療機関での治療が必要となることもあります。その場合、消化管機能改善薬などが処方されることがあります。
また、呑気症の背景に過度のストレスや緊張がある場合は、抗うつ薬や抗不安薬などの向精神薬が使用されるケースもあります。さらに、呑気症に伴って逆流性食道炎を併発することもあるため、胸やけなどの症状がある場合には、食道の状態も併せて検査してみるのが良いかもしれません。
胃腸炎
胃腸炎は、胃や腸の粘膜に炎症が生じる疾患です。この状態では、腸管がむくんで腸液が滞留するため、お腹が張ることがよくあります。
また、腸の一部のぜん動運動が低下してしまうことで、胃の内容物が腸へ円滑に送られず、結果として胃の張りを感じることもあります。
胃腸炎の治療には、まず胃薬の服用が有効です。これにより、胃腸の炎症を抑え、不快な症状を緩和することができます。併せて、消化に負担をかけない食生活を心がけることも重要です。具体的には、柔らかい食べ物や消化の良いものを選び、胃腸に優しい食事を心がけましょう。
回復期には、徐々に通常の食事に戻していくことが大切です。ただし、個人差もあるため、症状が長引く場合や、激しい腹痛、発熱などの症状がある場合は、医療機関への速やかな相談を検討しましょう。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで食道粘膜に炎症を引き起こす疾患です。この症状は食後2〜3時間ほどで起こりやすく、主な症状の一つとして腹部膨満感が挙げられます。胸やけや喉の違和感、げっぷの増加なども特徴的な症状です。
この疾患の治療の基本は、生活習慣の改善と胃酸の分泌を抑える薬物療法です。生活習慣の改善には、寝る前の食事を控える、食事の量を減らす、アルコールや刺激物を避けるなどが含まれます。薬物療法では、プロトンポンプ阻害薬や制酸薬などが用いられることが多いです。
胃酸を抑える薬だけでは症状が改善しない場合には、いくつかの薬を組み合わせて治療を行うことがあります。たとえば、胃の運動を改善する薬や、食道の知覚を鈍らせる薬を追加する場合もあります。症状が続く場合は、医療機関での精密検査を受けることを強くすすめます。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシア(FD)は、胃が張る症状が出やすい病気の一つです。この病気の特徴は、胃カメラで調べても炎症などの異常が見つからないにもかかわらず、お腹の不快感が続くことです。多くの場合、ストレスが原因だと考えられています。ストレスによって胃の動きが鈍くなり、食べ物をうまく十二指腸に送れなくなることで、胃の調子が悪くなるのです。
この病気の治療は、主に薬による治療と生活習慣の改善を組み合わせて行います。薬による治療では、胃の働きを良くするお薬や、胃の痛みを感じにくくするお薬を使います。これらのお薬によって、胃の不快感を和らげることができます。
一方で、生活習慣の改善も大切です。たとえば、ゆっくり食事をする、よく噛んで食べる、規則正しい生活を心がけるなどが効果的です。また、ストレス解消法を見つけることも大切です。気になる症状が続く場合は、かかりつけ医に相談してみることをおすすめします。
腸閉塞(イレウス)
腸閉塞(イレウス)は、腸の中を食べ物や消化物が通りにくくなる病気です。これは、腸がねじれたり、がんなどで腸の中が狭くなったりすることで起こります。腸の中に食べ物や消化物が詰まると、ガスもたまってしまい、その結果、お腹が痛くなったり張ったりします。
腸閉塞の症状は、詰まっている場所によって少し違いがあります。もし詰まっている場所が胃に近い側(口側)だと、吐き気や嘔吐が主な症状になります。この場合、お腹の張りはそれほど強くないことが多いです。一方、詰まっている場所がお尻に近い側(肛門側)だと、徐々にお腹が張ってくる感じがします。
腸閉塞は緊急性の高い病気です。激しい腹痛や、お腹が張る感じが続く場合は、すぐに医療機関を受診することが大切です。早めの治療により、重症化を防ぐことができます。日頃から、バランスの良い食事や適度な運動を心がけ、便秘にならないよう気をつけてみましょう。
胃潰瘍
胃潰瘍は、胃の内側にできる傷のような状態です。この病気になると、胃酸の分泌が少なくなり、その結果、腸の中にガスがたまりやすくなります。そのため、お腹が張る感じがよく起こります。また、胃の働きが弱くなって、食べ物を十二指腸へ押し出せなくなることもあります。すると、胃が異常に大きくなる「胃拡張」という状態になることもあります。
胃潰瘍の主な原因には、ピロリ菌という細菌の感染や、強いストレスがあります。ピロリ菌は胃の粘膜を傷つけ、ストレスは胃酸の分泌を増やすため、どちらも胃を傷つける原因となります。
治療中は、胃に優しい食事を心がけることが大切です。特に、炭水化物やたんぱく質は、胃潰瘍を治すのに必要な栄養素です。お腹の張りや痛みがある間は消化しやすい食事を選び、徐々に栄養バランスの良い食事に戻していくとよいでしょう。気になる症状が続く場合は、専門医による適切な診断と治療を検討しましょう。
胃がん
胃がんは、胃の中にできる悪性のしこりのことです。初期の段階では自覚症状がほとんどないため、気づきにくい病気です。しかし、がんが進行すると、胃の出口や内側が狭くなることで、お腹が張る症状が現れやすくなります。
胃がんの症状は、進行具合によって異なります。初期では、むねやけや胃のもたれ感など、日常的によくある症状と似ているため、見過ごされがちです。進行すると、食欲不振、体重減少、吐き気、腹痛などの症状が現れることがあります。しかし、かなり進行しても目立った症状がない場合もあり、そのため発見が遅れることもあります。
お腹の張りが長く続いたり、食事の際に違和感を覚えたりする場合は、一度検査を受けてみることを検討してください。特に、50歳を過ぎたら定期的な胃の検診を受けることが大切です。
腹部膨満感の苦しさを解消する方法
胃の張りは、生活習慣の改善で自然に治まることがほとんどです。
しかし、中には消化管の疾患を原因に引き起こされるケースもあるため、症状が長引くようであれば、できるだけ早めに病院を受診しましょう。
食生活の改善をして胃の負担を減らす
胃が張るときは、食事や飲み物の内容に工夫しましょう。
温かくて柔らかく、脂質の少ないものを選ぶと胃に負担がかかりにくくなります。また、食物繊維の少ない野菜も消化に良い食品です。長時間加熱を意識した調理を行い食材を柔らかくしてから食べましょう。
飲み物では、アルコールやカフェインが多い飲み物は胃酸で胃が荒れやすくなるため注意が必要です。
心身ともにリラックスさせて副交感神経を優位にする
胃の働きは、自律神経の1つである副交感神経によって調節されています。
副交感神経が優位になると胃の働きが活発化し、胃酸の分泌が増えて消化管の運動が促進されます。
胃の働きを改善するには、副交感神経を優位にすることが大切です。
ぬるめのお湯でゆっくり入浴したり、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れるといいでしょう。身体を動かす習慣をつけると、副交感神経が優位になり、胃の働きを促進する効果が期待できます。
医療機関の受診が必要な症状
胃がパンパンに張って苦しいときは、下記のような症状にも注目しましょう。
- 息苦しさや圧迫感がひどい
- 痛みがひどい
- 発熱がある
- 症状が治まらない
- 嘔吐している
- 冷や汗が出ている
- けいれんしている
- 意識障害がある
- 突然強い膨満感が起こった
お腹の張りを自己判断すると、病気を見逃すことにつながります。
消化器内科を受診して、超音波検査や内視鏡検査、CT 検査を受け、原因に合わせた治療を行いましょう。
東京23区で胃の張りが続いている方は東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックへ
胃がパンパンに張る症状は、多くの場合、生活習慣の改善で和らぐことがあります。消化の良い食事を心がけたり、適度な運動習慣を取り入れることで改善が期待できます。
また、消化器はストレスの影響を受けやすい器官でもあるため、リフレッシュの機会や趣味の時間を大切にし、ストレスをため込まないことも胃の張りの改善に効果的です。
しかし、症状が長期間続く場合は、放置せずに専門医による診断を受けることが重要です。東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでは、高度な専門性を持つ医師による内視鏡検査を実施しています。最新のメディカルウェアを導入し、患者さまの負担を軽減しながら精密な検査が可能です。
女性専用スペースも完備しております。プライバシーに配慮した環境で、女性の方も安心して検査を受けていただけます。また、他医療機関で検査時に苦痛を感じた経験のある方も、当院の熟練した技術と丁寧な対応で、より快適に検査を受けることができます。
胃の不調でお悩みの方、特に長期間症状が続いている方は、ぜひ当クリニックにご相談ください。
電話でのご予約も9〜17時で承っています。
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分