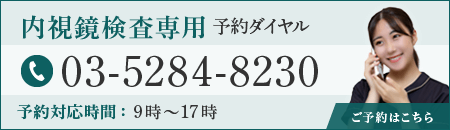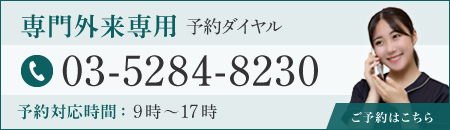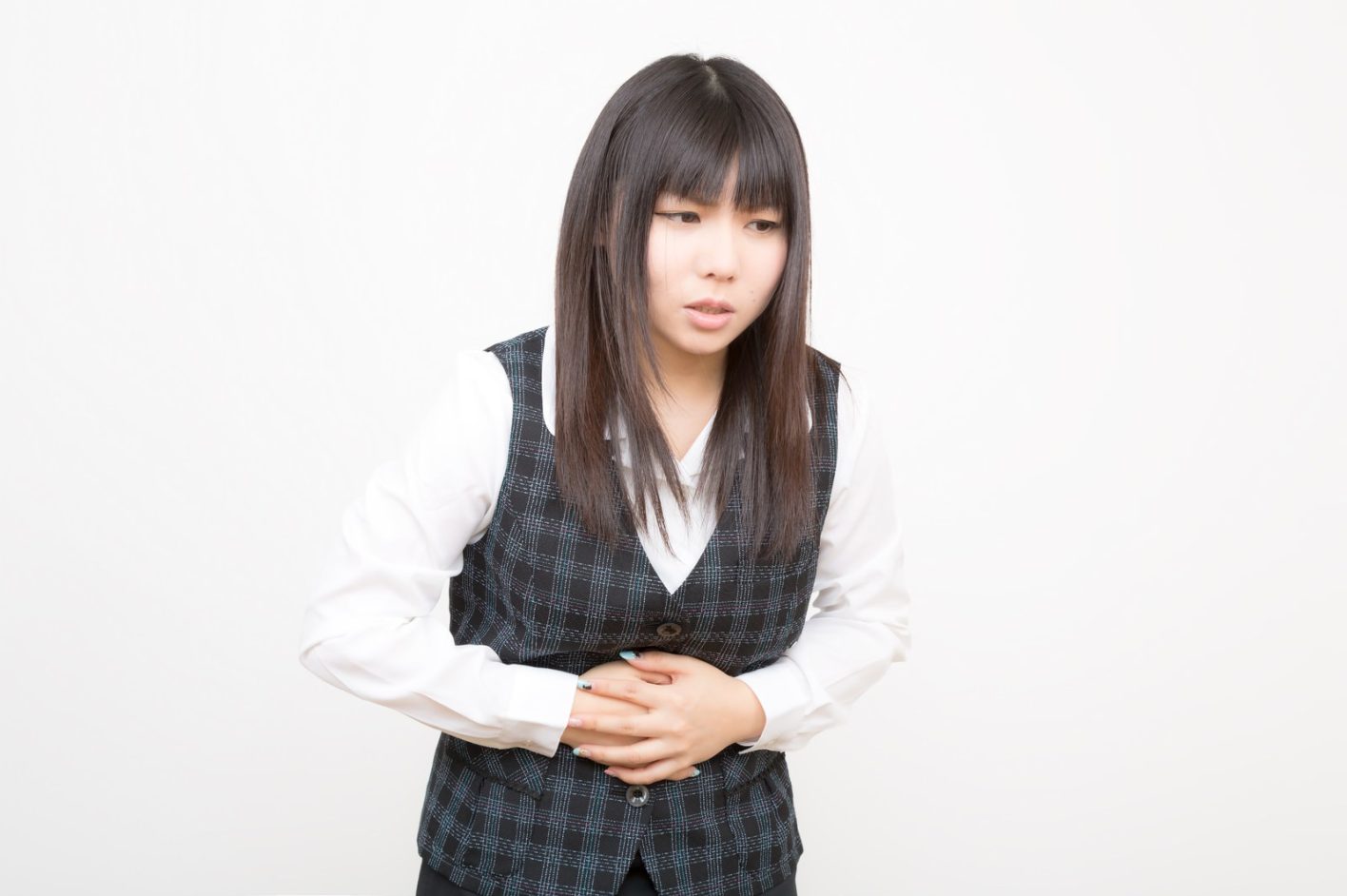
「下痢をしていたのに、急に便が出にくくなった」
「下痢と便秘をくり返すときはどうしたらいいの?」
下痢が続いていると思ったら、急に便秘になることはありませんか。お腹を壊しているはずなのに、便の出が悪くなるなんて心配になってしまいますよね。
下痢の後に便秘が続く症状は、多くの人が経験する消化器系のトラブルです。この症状の背景には、腸内環境の変化や自律神経の乱れ、日々のストレスなど、さまざまな要因が関与している可能性があります。もしかしたらこれは一時的な体調不良だけでなく、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患といった慢性的な疾患のサインかもしれません。
このような症状でお困りの方には、東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでの診察がおすすめです。当クリニックは消化器疾患の診断に豊富な経験を持ち、最新の内視鏡技術を駆使して、下痢と便秘を繰り返す原因を丁寧に調べます。女性の方も安心して受診できるよう、専用の検査エリアを設けており、女性医師による診察も可能です。
アクセスの良さも魅力の一つで、JR北千住駅から徒歩2分の場所にあります。平日だけでなく週末も診療を行っているため、お仕事で忙しい方も通いやすいでしょう。さらに、オンラインでの24時間予約システムを導入し、待ち時間の短縮に努めています。
まずはお気軽にご相談ください。
目次
下痢のあとに便秘になりやすい病気
下痢のあとに便秘になりやすい疾患には、大腸がんや過敏性腸症候群などがあります。
いずれも症状が分かりにくい疾患のため、早めに医療機関を受診して検査を受ける必要があります。
大腸がん
大腸がん(結腸がん・直腸がん)は、大腸(結腸・直腸)に発生するがんのことです。
腺腫と呼ばれる良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。
大腸がんの初期段階に、自覚症状はほとんどありません。進行すると症状が現れやすくなり、便秘や下痢をくり返すようになります。なお、下痢をしたあとに便秘する際には、左側結腸にがんが生じていることが多いです。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(IBS)とは、消化器の疾患がないにもかかわらず、便秘や下痢を慢性的に繰り返す疾患です。腸管の動きが亢進し、刺激への反応が過敏になることで引き起こされると考えられています。
主な原因はストレスや不安といった心理的要因や、自律神経の失調とされています。また、生活習慣の乱れも消化器症状を起こしやすい要因の1つです。
下痢のあとの便秘を解消する方法
下痢のあとの便秘を解消するには、こまめな水分補給や便通を整えることが有効です。
また、お腹を温めることで血行が良くなり、腸の働きが活発になることもあります。
こまめに水分補給をする
便秘や下痢を繰り返す場合、水分補給が非常に重要です。便秘時には十分な水分摂取により便が柔らかくなり、排便がスムーズになります。一方、下痢の際には脱水症状を予防するために水分補給が欠かせません。
体内の水分不足は腸壁の水分吸収を妨げ、下痢を引き起こしやすくなります。また、脱水症状は腸の運動を過剰に活発化させ、便の急速な通過を招きます。
これらの理由から、便秘と下痢のどちらの場合も、こまめな水分補給を心がけることが大切です。水やお茶などカフェインの少ない飲み物を選び、1日に1.5〜2リットル程度を目安に摂取しましょう。
トイレには我慢しないで行く
便秘解消のためには、便意を感じたらすぐにトイレに行く習慣をつけることが重要です。我慢しすぎると腸の活動が鈍くなり、便意を感じにくくなってしまいます。便意がなくても、毎日決まった時間にトイレに行き、排便する習慣をつけることも効果的です。
特に朝食後は腸の蠕動運動が活発になりやすいため、自然と排便しやすい状態になります。この時間帯を利用して、ゆったりとした気持ちでトイレに向かいましょう。一方、下痢の場合は無理に我慢せず、体外に出すことが大切です。
お腹を温める
お腹を温めることは、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。慢性的な便秘や下痢の症状緩和にも役立ちます。温めることで腸の血行が良くなり、腸内環境が整いやすくなるのです。
お腹を温める方法には、温タオルや湯たんぽ、腹巻きなどがあります。使用する際は低温やけどに注意し、タオルで包んだりパジャマの上から使用したりするなど工夫しましょう。1日20〜30分程度、就寝前などリラックスできる時間帯に行うのがおすすめです。継続することで腸の動きが活発になり、自然な排便リズムを取り戻すことができるでしょう。
下痢のあとに便秘にならないための予防法
下痢のあとに便秘にならないためには、十分な量の食物繊維を摂取したり刺激物を控えたりすることが効果的です。
また、消化器症状はストレスの影響を受けやすいため、リラックスする時間を確保することも大切です。
食物繊維を摂る
便秘にならないためには、食物繊維を積極的に摂取することが効果的です。
食物繊維には、便のかさを増やす「不溶性食物繊維」と、便を軟らかくする「水溶性食物繊維」があり、便秘のタイプによって摂取するべき食物繊維が異なります。
不溶性食物繊維は、大腸で水分を保持して便のかさを増やして腸を刺激します。代表的な食材は、以下の通りです。
- ごぼう
- レンコン
- 豆類
- おから
- きのこ
一方で、水溶性食物繊維は便に水分を増やす効果があります。代表的な食材は以下の通りです。
- ヨーグルト
- チーズ
- キムチ
- 納豆
これらの食物繊維を含む食品をバランスよく摂取することが重要です。ただし、急激に食物繊維の摂取量を増やすと、かえって腹痛や膨満感を引き起こす可能性があるため、徐々に増やしていくことをおすすめします。また、食物繊維を摂取する際は十分な水分摂取も忘れずに行いましょう。
刺激物を控える
刺激の強い辛い食べ物や、コーヒー、アルコール類は腸に刺激を与えるため、控えたほうがいいでしょう。
冷たい食べ物や飲み物も下痢を助長します。冷たいものや冷たい食べ物、飲み物は下痢を助長します。
ストレスを溜めすぎない
ストレスが溜まると、便秘や下痢が悪化することがあります。
ストレスによって自律神経が乱れると、排便をするときに優位になる副交感神経の働きが抑制されてしまうため、交感神経が優位になり排便が難しくなってしまうのです。
ストレスが原因の便秘や下痢には、便秘薬や食物繊維といった一般的な対策が通用しにくいことがあります。そのため、ストレスによって受けたダメージを回復するために、ストレスを溜めない生活を心がけましょう。規則正しい生活や十分な睡眠時間を確保することも、ストレス軽減に有効です。
下痢と便秘を繰り返すときの受診のタイミング
大腸がんの位置によって症状が異なりますが、下行結腸やS状結腸、直腸にできる大腸がんでは便の通りが悪くなることで便秘が起こりやすくなります。
また、大腸がんが進行すると腸閉塞が引き起こされ、血便や嘔吐といった症状も現れます。腸管の壊死が起こる可能性が高くなるため、できるだけ早い治療が必要です。
下痢と便秘でお悩みの方は東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックへ
下痢のあとに便秘を繰り返す症状には、潜在的な病気が隠れている可能性があります。ストレスや不安が原因の一過性のものであれば、時間とともに症状は落ち着くかもしれません。
しかし、長期間にわたる下痢と便秘の繰り返しは、消化器官だけでなく身体全体に大きな負担をかけます。このような症状が続く場合は、早めに専門医による診断を受け、適切な治療を開始することが重要です。
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでは、大腸がん検診はもちろん、胃や食道の内視鏡検査にも対応しています。当院には内視鏡専門医が在籍しており、静脈麻酔を使用した大腸内視鏡検査を行っています。そのため、他の医療機関で不安や恐怖を感じた経験のある方も、安心して検査を受けていただけます。静脈麻酔により、うとうとした眠気を感じながらリラックスして検査を受けることができます。
当クリニックは、JR北千住駅から徒歩2分という好立地にあり、土日も診療を行っているため、忙しい方でも通いやすい環境です。また、女性専用の検査スペースも完備しており、デリケートな症状でも安心してご相談いただけます。
検査および診察のお申し込みは、24時間対応のWEB予約システムまたはお電話から受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
電話でのご予約も9〜17時で承っています。
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分