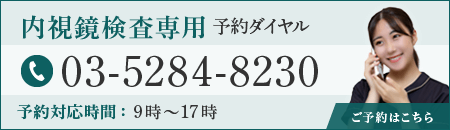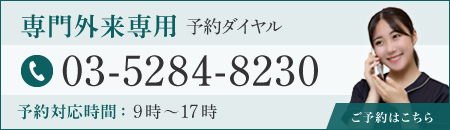「真っ赤な血便が出た」
「血便が出たらどうしたらいいの?」
急に真っ赤な血便が出るとビックリしてしまいますよね。そして、何か病気なのではないかと不安になってしまうでしょう。
真っ赤な血便には、鮮血が混ざっています。
鮮血が混ざる便は、肛門から近いところの直腸や痔を原因とすることがほとんどです。一過性のものもありますが、血便が続くときや症状が不安なときは医療機関を受診しましょう。
今回は、真っ赤な血便の原因や緊急性、対処法について解説します。
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでは、最新の内視鏡技術を用いて、血便の原因を正確に診断します。当クリニックには、経験豊富な医療スタッフが在籍しており、患者さん一人ひとりに寄り添いながら検査と診断に携わっています。
高精細な画像を提供する最新の内視鏡機器を使用し、小さな病変も見逃さず診断が可能です。さらに、女性の方も安心して検査を受けられるよう、女性専用スペースを設けています。JR北千住駅から徒歩2分という好立地で、土日も診療を行っているため、忙しい方でも通いやすい環境です。
血便の症状がある方は、早めの受診をおすすめします。東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでは、24時間WEBでの予約受付を行っており、スムーズに検査を受けていただけます。
目次
血便とは?
血便とは、消化管からの出血が原因で便に血が混じる状態のことです。
出血する部分によって、便の色や状態が異なります。
肛門に近い大腸からの出血では真っ赤な鮮血便(血便)、胃や十二指腸からの出血では肛門便として排出されるまでに時間が経過しているため、タール状の黒色便(下血)になります。また、血液は胃酸と反応したり、腸からの消化液が混ざったりすることもあり、暗赤色や粘血便になることもあります。
多くの場合、真っ赤な血便は痔出血を原因としています。しかし、危険な疾患のサインである可能性も高いため、医療機関を受診するといった対処が必要です。
真っ赤な血便が出たらすぐに医療機関へ
真っ赤な血便が出た場合は、消化器内科や内視鏡クリニックといった医療機関を受診しましょう。便に鮮血が混じっていたり便器に血が付着したりするだけでなく、下着やトイレットペーパーについた血も対象です。
血便は消化管のどこかに疾患が起きていることを示しているため、放置すると潰瘍や穿孔といった重篤な疾患に悪化することがあります。また、出血量が多いと貧血を招き、めまいや冷や汗を伴うなど重症化も避けられません。
真っ赤な血便から考えられる病気について
真っ赤な血液が混じる鮮血便は、肛門や直腸などから出血したばかりの血液が混じっています。鮮血便は、肛門や直腸のトラブルによるものが多く、原因となる疾患には痔核や大腸がん、直腸ポリープなどがあります。
痔核(いぼ痔)
痔核(いぼ痔)は、排便時に鮮血便となる原因の1つです。痔核は、長期的な便秘や下痢が原因となり、肛門に負担がかかることでうっ血した状態です。
排便時のいきみで、肛門や直腸の粘膜が傷ついて出血します。出血量は、トイレットペーパーや便に少量つく程度からほとばしる程度までさまざまです。とくに内痔核は、初期段階では出血量が多くありませんが、症状が進行すると量が増えていきます。
治療には、生活習慣の改善や軟膏の使用が一般的です。重症の場合は、手術が必要になることもあります。適切な治療により、多くの場合で症状の改善が期待できるでしょう。
裂肛(切れ痔)
鮮血便の原因として考えられる裂肛(切れ痔)は、硬い便が出たときに肛門に傷ができた状態です。鮮血便の原因として頻繁に見られる症状です。
排便時に痛みを伴い、トイレットペーパーに鮮血が付着します。また、排便後も肛門に違和感や強い肛門痛を伴う特徴があります。便秘や下痢が続く場合に発症リスクが高まります。
治療には、軟膏の塗布や座浴が効果的です。また、便を柔らかくする薬を使用することもあります。重症の場合は手術を検討することもありますが、多くは保存的治療で改善が見込めるでしょう。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎(UC)は、大腸の粘膜が傷ついて出血しやすくなる慢性の炎症性腸疾患です。免疫系の異常が原因と考えられています。
便に血液が混じることが多く、ほとんどが鮮血に近い血便となります。軽症だと少量の血便が出る程度ですが、重症になると真っ赤な血便が出続けます。痔と区別がつきにくいこともありますが、UCの血便は赤黒い場合が多いです。
治療には、炎症を抑える薬物療法が主に用いられます。症状の程度に応じて、経口薬や注射、坐薬などが使用されます。寛解維持療法も重要で、長期的な管理が必要となるでしょう。
直腸潰瘍
鮮血便の原因には、直腸潰瘍による急性出血性直腸潰瘍が考えられます。大量の真っ赤な血便を特徴としています。主に高齢者や全身状態の悪い患者さんに発症します。
脳腫瘍といった脳の病気や、肺炎や腎不全などの疾患を理由に長期間臥床していると発症リスクが高まります。主に、70歳以上の高齢の方で、全身状態や栄養状態が悪いときに発症しやすいとされています。
治療には、まず出血のコントロールが重要です。内視鏡的止血術や薬物療法が行われます。また、原因となっている基礎疾患の治療や、栄養状態の改善も必要となるでしょう。
直腸ポリープ
直腸ポリープは、大腸の粘膜がいぼ状に隆起した状態を指します。便が通過する際に表面が傷つくことで出血し、鮮血便の原因となります。
血便の色は暗めの赤色から鮮やかな赤色までさまざまです。ポリープが大きくなるほど、出血のリスクが高まる傾向がありますが、多くの場合、目に見えるほどの大量出血はありません。気付きにくい少量出血が多いため、便潜血検査で発見されることもあります。
治療には、内視鏡的ポリープ切除術が一般的です。大きさや性状によっては、外科的切除が必要になる場合もあります。定期的な検査で早期発見・早期治療が重要でしょう。
直腸がん
直腸がんは肛門に近い部位に発生するため、鮮血に近い血便が初期症状として現れることが多い疾患です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、早期発見が難しいのが特徴です。
硬い便が腫瘍のある部分を通過する際に出血し、血便となって気付くことが多いです。出血が増えると貧血や動悸、ふらつきを感じることもあります。また、便通異常や腹痛なども症状として現れることがあります。
治療方法は、がんの進行度によって異なります。早期の場合は内視鏡的切除や局所切除、進行している場合は手術療法が主となります。必要に応じて放射線療法や化学療法を併用することもあるでしょう。
血便の原因を特定する検査方法
血便の原因を検査で特定することで、症状に応じた治療を行えるようになります。
真っ赤な血便が出る際には、直腸診やCT検査、内視鏡検査が有効です。
直腸診
血便の原因の多くは肛門に近いところからの出血であるため、肛門や直腸の状態を確認する直腸診が重要です。直腸診は、肛門や直腸の状態を確認し、腫瘍および痔核の有無を確認できます。
直腸診を行う際には、医師が手袋を着用して、麻酔ゼリーを塗布した肛門から直腸にかけて触診し出血を確認します。
CT検査
血便が出た場合、小腸腫瘍からの出血や大腸憩室出血が疑われるケースでは、CT検査を行うことがあります。
また、クローン病と診断するための小腸の状態評価が必要な場合や、胃がんおよび大腸がんの転移状態を調べる際にも活用します。
大腸内視鏡検査
血便や下血は腸管内からの出血を意味するため、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)を行い、腸管粘膜の状態を確認することが大切です。
大腸内視鏡検査は、大腸の腫瘍や炎症など大腸内での病変が疑われるときに選択されます。
なお、大腸がんは早期発見をすれば、適切な治療を受けて完治する疾患です。また、前がん病変のポリープ切除を行って、大腸がんの予防も可能です。
血便とストレスの関係について
ストレスは、直接的に血便の原因にはなりません。
しかし、ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、消化管機能が低下して下痢や便秘を繰り返しやすくなります。そうすると、血便が出やすくなるのです。
消化器に負担がかかることで、潰瘍ができやすくなることもあります。
また、精神的ストレスが原因とされる過敏性腸症候群を発症すると、下痢や便秘を引き起こし、排便時にいきみ過ぎることでいぼ痔や切れ痔を発症して、血便が出る場合があります。
真っ赤な血便を予防するには?
真っ赤な血便の予防には、便通の改善が近道です。
硬い便が柔らかくなることにより、直腸や肛門周辺を傷つけて出血するリスクが低下します。
また、ピロリ菌を原因としているときには除菌をし、定期的な検査を行うことも大切です。
便秘に気を付ける
便秘は血便の原因の1つとして挙げられます。便秘になると、便の水分量が減少して硬くなり、直腸や肛門を傷つけて出血する可能性が高まります。また、腸にかかる負担が増えると、大腸疾患や内痔核を発症するリスクも上昇します。
予防には、規則正しい生活を送ることが大切です。食事やストレスにも注意して、便秘対策を行うようにしましょう。便秘は慢性化しやすい症状ですが、適切な対策で改善が可能です。
症状が続く場合は、消化器科での専門的な治療を検討することをおすすめします。医師の指導のもと、適切な治療法を見つけることで、便秘の解消が期待できるでしょう。
ピロリ菌除菌治療を受ける
ピロリ菌感染は、胃や十二指腸の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。放置すると潰瘍化することもあり、治療しても再発を繰り返しやすいのが特徴です。潰瘍で粘膜が深く傷つくと出血し、血が混じった黒いタール状の便が出ることがあります。
ピロリ菌に感染している場合は、除菌治療が必要です。治療は抗生物質と胃酸分泌を抑える薬の服用で行います。1回目の除菌治療で約8割の方が成功しますが、完了していない場合は抗生剤の種類を変更して2回目の治療を行います。
1回目と2回目を合わせた除菌治療の成功率は99%程度と高いです。除菌治療により、胃炎や潰瘍のリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
定期健診を受ける
血便の予防には、定期的な健診が有効です。血便の原因となる消化管出血は、大腸がんや胃がんなどが背景にあることがあります。これらの疾患は自覚症状が乏しく、血便などの症状が現れたときには進行しているケースが多いです。
定期的な内視鏡検査を受けることで、早期発見や進行度合いに応じた治療が可能になります。胃カメラでは粘膜の状態やピロリ菌感染の有無を調べられ、大腸カメラでは前がん病変の大腸ポリープを発見し、検査中に切除することもできます。
健診を通じて、胃がんや大腸がんのリスクを早期に把握し、適切な予防策や治療法を講じることができるでしょう。定期的な検査で、自身の健康状態を把握することをおすすめします。
血便の相談は東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックへ
真っ赤な血便は、多くの場合、痔や直腸の疾患が原因です。しかし、大腸ポリープや大腸がんなど、より深刻な病気の可能性も否定できません。生活習慣の改善や便秘対策を行っても出血が続く場合は、早めに専門医による診断を受けることが重要です。
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックは、2022年に10,654件の内視鏡検査実績を持つ、消化器疾患の診断に豊富な経験を有する医療機関です。当クリニックでは、最新の内視鏡技術を用いて、血便の原因を正確に診断します。検査を受けた方の95%が「全く痛くなかった」と回答しており、快適な検査環境を提供しています。
特に女性の方への配慮に力を入れており、女性専用の検査スペースを完備し、肌の露出が少ないメディカルウェアを採用しています。また、女性医師や女性の超音波検査士も在籍しているため、デリケートな部位の検査でも安心して受診いただけます。
JR北千住駅から徒歩2分という好立地で、土日も診療を行っているため、忙しい方でも通いやすい環境です。24時間WEBでの予約受付も行っており、待ち時間の短縮にも努めています。
真っ赤な血便の診療を検討されている際には、ぜひ当クリニックにご相談ください。
電話でのご予約も9〜17時で承っています。
施設紹介
東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>
ホームページ https://www.senju-ge.jp/
電話番号 03-3882-7149
住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
※予約検査のみ
※祝日のみ休診
JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分